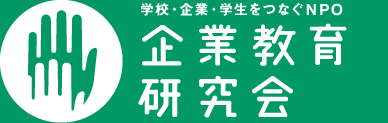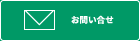2025年5月24日、「第169回 千葉授業づくり研究会」が開催されました。今回のテーマは「生成AIを活用したこれからの授業のあり方」です。
生成AIについては、この授業づくり研究会でも繰り返し取り上げています。
【第161回】千葉授業づくり研究会のようすをご紹介します:「生成AIを活用した創造的な授業とは?!」
【20周年記念イベントレポート】⑦生成AIの活用
開会のあいさつでACE理事長・藤川教授からも「生成AIはインターネット以来の人間の重要な発明であり、我々の生活を大きく変化させていくことでしょう。そんな変化していく社会を生きていく子供たちを育てる教育現場が、生成AIによってどう変わっていくのかを考えることはとても重要なテーマです。」と話がありました。
これから、学校教育に生成AIはどのような影響を与えるのでしょうか。
講師には、教育現場での生成AI活用において先駆的な取り組みを進めるNPO法人みんなのコードより、竹谷正明さん(元・みんなのコード)、永野直さんをお招きしました。お二人からは、小学校から高校までの具体的な実践事例を交えながら、生成AIという存在をどう捉え授業に活用しているのかなど、示唆に富むお話をいただきました。
国の動向と教育現場への方針:文部科学省の「積極的な利活用」への動き
竹谷さんは、まず、生成AIに関する国の動きについて分かりやすく解説されました。
生成AIについて、文部科学省の対応は「早かった」と竹谷さんはおっしゃいます。
2023年7月のガイドライン公表、9月のパイロット校指定と続き、さらに、2024年12月の次期学習指導要領へ向けた諮問では「生成AIという言葉が7か所も記載」されるなど、文部科学省が生成AIを今後「積極的に利活用することが有用」という方針を、明確に示していると説明しました。
しかし、その活用については児童生徒に「突然使わせても難しい」ため、生成AIそのものを学ぶこと、利活用することを学ぶことなど、活用の意味を考え、それぞれの教科等を関連付けていく必要があると指摘しました。
さらに、文部科学省が示す「情報活用能力の育成強化」に触れ、今後は生成AIの存在を前提とした教育になっていくと思われることや、東京都では全ての都立学校に生成AIが導入されるなど(都立AI)、すでに教育現場へ生成AIが大規模、かつ加速的に導入されていることも紹介しました。

また、ベネッセ2024年6月の調査データから、「1割の小学生が生成AIを使っている」という実態を紹介し、この状況を踏まえ、「小学校段階からのAIリテラシー教育」を「公教育でやっていく必要性」と、子どもたちが生成AIに対して「実感を伴い自律的に判断できる力」を得るには、個々人で使っていてもひとりでに学ぶことは難しく、学校で、安全な場で仲間や教師と学ぶことが必要だと考えていることを教えてくださいました。
日本教育新聞:次期学習指導要領で「情報活用能力育成」を一層強化
東京都教育委員会・都立AIについて
ベネッセコーポレーション 「生成AIの利用に関する調査」2024
「みんなで生成AIコース」:安全な環境下での体験学習
このような状況を解決するため、みんなのコードでは、教育現場向けの「みんなで生成AIコース」を提供しています。
このコースは、送信データが生成AIの学習に利用されないなどの一般的な安全性に加え、「教師が児童の会話履歴を確認することが可能」「利用に際し生徒児童の個人情報が不要」「教師がアカウントを作成する」「アクセス可能時間を設定できる」といった特徴が備わっています。「先生が監督責任を持つことで年齢制限なく使用できる」ことで、使用に年齢制限がある生成AIを小学校でも安心して活用できるようになっています。
「みんなで生成AIコース」小学校での実践事例:印西市立原山小学校5年生・8時間の実践
次に、「みんなで生成AIコース」を活用した小学校5年生への実践事例が紹介されました。
授業はAIに“学ばせる”体験から。
Googleが提供する「Teachable Machine」を使用し、子どもたちが撮影した国旗写真より、AIに国旗の種類を学ばせるという活動からスタートしました。
竹谷さんは、「国旗は誤認識が少ない」ため、機械学習の基本的な原理をスムーズに理解できると言います。そして基本的な原理を学んだ後、子どもたちは「自分が認識させたいもの」を自ら考えました。
これらの体験を通した授業を進める中で、教科書を認識させ、持ち物を確認する「忘れ物防止」アプリを作成する子どももでてきたそう。竹谷さんは、こういう体験を通して、子どもたちが自分もAIを使って何かできそうだ!という感覚を作っていけると良いのではとお話しされました。
生成AIを前に子どもたちがどう反応するかの傾向としては、まずはインターネットのキーワード検索のように、検索的にAIを活用し、そのうちしりとりなどして生成AIと遊びだすとのこと。そして、だんだん物語や音楽を作らせるなど、自然とクリエイティブな使い方をしていくそう。もちろんこの小学校での実践においては、子どもたちは生成AIと遊ぶ以外にも、国語で意見文の添削をお願いするなど、さまざまな教科の学習場面で生成AIを使う体験を重ねました。
そして、この実践を1年間継続した子どもたちが6年生に進級した際には、「生成AIを相棒にしよう」をテーマに、さらに活用を進めました。
例えば国語の単元では、「学校のお昼ご飯は給食と弁当のどちらがいいのか」と議論する場で、生成AIに意見を添削してもらう形で生成AIを活用しました。その際、子どもたちが、自分たちの主張をより説得力のあるものにするため、どんな資料を追加すべきかアドバイスを求める例も見られました。そして、だんだん給食費や栄養バランスなど、生成AIのアドバイスを参考にしつつも、生成AIを離れて調べる子どもの様子も見えたとのことです。
授業のふりかえりや感想では、「算数は、答えを教えてもらうんじゃなくて解き方を教えてもらうのが必要」「なんのために使うのか、それを使って何になるのかを考える」「出てきたものが本当に正解か一度考えることが大事」「自分が正しい使い方をしているのか自問自答しながら使っていきたい」等の意見が出ました。
竹谷さんは、「全員こういうこと気づくわけではないけれど、クラスの中にそういう子がいることが大事」と言います。アンケートでも、「みんなと使ったから自信ついた」と7割の子どもが回答したと紹介しました。
小学校段階における生成AI活用の留意点
実践紹介の後、小学校段階で生成AIに触れる上で、小学生に意識させるべき「留意点」についても説明しました。
⮚ 人格を求めない
子どもたちが生成AIに過度な期待を抱いたり、人間のような感情や意志があるかのように認識したりしないよう、その特性を正しく伝えることが重要。
⮚ 検索エンジンと生成AIの違いの認識
生成AIは「知識を問う」キーワード検索のような使い方には向いていません。その原理の違いを理解し、より「高次の利用を指向すること」が求められます。
⮚ 事実かどうかの確認
こちらは「生成AIに限らない」と強調されました。インターネット上のあらゆる情報と同様に、生成AIの情報を鵜呑みにせず、常に信憑性を確認する姿勢が必要です。
高校での実践事例について
次に、永野さんから、高校における生成AI活用の具体的な実践事例をご紹介いただきました。
2011年当初、日本初一人一台端末を導入した情報科教員であったという永野さん。 永野さんは、「すでに産業界では、生成AIは当然に使われている。便利であるからこそ、教育界でどう使っていくにはというところは議論がありますが、ただ、インターネットが生まれた時と同じで、生成AIを今後使っていく未来は確定なので、本当に子どもたちをそこから隔離することは良いことだとは思いません。危なさがあるのであれば、それを知らせ、どう対処するか伝えることが教育なのでは」とおっしゃいます。使う心配も、使わない心配もあるものの、生成AIを避けるのではなく、過信も不信も防ぐことが重要であると説明しました。

先生に伝えていること:効果的な活用に向けて
そして、永野さんが、生成AIの活用について現場の先生方へ伝えていることを紹介くださいました。
⮚ 検索エンジンと生成AIの違いを明確にすること
子どもたちは無意識のうちにキーワード検索のように使う傾向がありますが、これは生成AIには不向きな使い方。
⮚ ハルシネーション(誤情報生成)について
ハルシネーションが問題になるのは、そこにファクトを求めるから。事実確認、計算、用語の意味確認には不向き。アイデアを得る、視点を広げる、参考にする等の活用が効果的。
※ハルシネーションについては「すごい勢いで減っている」としながらも、「すべてを信用していいとは今後もならない」と指摘しました。
⮚ 効果的な活用について(意図した回答を得るプロンプトの改善)
ある程度長いプロンプトが必要になってくるものの、現代の子どもたちが長い文章をきっちり書かない傾向にあることも指摘。言語能力はAIについても重要で一層求められる。
※プロンプト:プロンプトとは、AI(人工知能)に「こうしてほしい」「これについて教えてほしい」とお願いするときに使う「指示」や「命令」のこと。

対象年齢の違いにより表現は違いますが、小学生向けの留意点を説明された竹谷さんと大枠は同じことを指摘されている気がします。これらのポイントは、どの年齢に対しても、生成AIを活用する大きなヒントとして参考になりそうです。
具体的な実践事例について
続いて、高校における具体的な実践事例について4つの事例を紹介されました。
1.生成AIと生徒のディベート:生成AIを反対の立場に立たせて活用する事例。「友達と反対意見を言い合う」のは生徒にとってハードルが高くても、生成AIを活用して「喧嘩をするのではなく意見を聞く、反論する」という経験を積むことができます。永野さんは、生徒が自分のことを伝えられるようになるには、ある程度経験が必要だと考えていらっしゃり、その機会を多く得ることに生成AIを活用。
2.時事問題を読んで考察文を書く:朝学習などで、その日の新聞記事について短い考察文を書き生成AIに添削してもらう活動。この実践では、「先生が小論文の添削をするのは大変だけれど、生成AIならたくさんできる」という教育現場の負担軽減と、生徒の学習機会の増大という両面で大きなメリットがある事例。
3.探究学習での活用:探究は調べ学習と違い、問いを立てる必要があります。生成AIは、その際に、「考えを整理するのに使うのが有効」だと紹介。生徒と生成AIとで、興味のあることなどを会話させテーマを決めたり、仮説の反対意見を聞いたり、そのテーマで進めると何が分かるのか、困難な点は何かを問うなど、探究学習の各段階で生成AIを活用。
4.生成AIとプログラミング:生成AIとプログラミングは「親和性が高い」分野であるものの、AIはプロが使うような効率的な正解を提示してしまい、学習としては意図が違ってしまう場合もあります。みんなのコードでは、高校情報向けのプログラミング教材に生成AI機能を追加し、生成AIが正解のコードをそのまま生徒に提示しない工夫をしています。また、プログラミングの授業では生徒が基礎的な質問を躊躇う場面や、先生への質問待ちで作業が進まない場面もあり、そういう時にも生成AIは質問先の1つとして有効。
授業としての情報、プログラミングなどは、例えば自由課題として何か作りたいと思っても、知識技能の習得が壁となり、楽しさに行きつくまでに嫌になってしまうこともありました。ですが生成AIが登場した今は、まずは作ってみてから、生成AIの助けを借りつつ修正するなど、学習の順序が変換する可能性があるとのこと。永野さんは、技術系の授業のあり方が変わるのではないかと期待しているとお話しされました。
また最後に、生成AIは使い方に大きく左右され、AIをより良い方向に活用するためには、単にAIの使用を禁止するのではなく、学校現場がより良い使い方を、(生徒が)自ら考えられるようなヒントを与え、関わっていく必要がある。
AIが簡単に「それらしいもの」を作れるようになる現代において、人間が何かを創造する際に最も大切なのは、あなた自身の経験、感情、「これが好きだ」というこだわりを持っているか、またそれが作品に表現されているかどうかだと思うと締めくくりました。


◆ディスカッション
研究会の後半は、千葉授業づくりでは定番のディスカッションの時間です。生成AIの教育現場への導入に際し、参加者から活発なディスカッションが行われました。
ここからは、ディスカッションの内容を一部抜粋要約してご紹介します(敬称略)。



今回の研究会を通じて、生成AIが教育現場にもたらす可能性と課題、そしてこれからの授業のあり方について多角的に知ることができました。生成AIの進歩は目覚ましく、数か月後には状況が変わっているかもしれません。今後もその動向を注視し、教育への最適な導入方法を模索していく必要があると感じました。
以上で、第169回千葉授業づくり研究会のレポートのご報告とします。ご講演いただきました竹谷さんと永野さん、そして参加者のみなさま、ありがとうございました。
千葉授業づくり研究会の参加方法
千葉授業づくり研究会にはどなたでも参加できます。
興味がある方は、こちらの開催情報をチェックしてくださいね!Zoomを用いたオンライン配信による参加もできるので、遠方の方も大歓迎です。