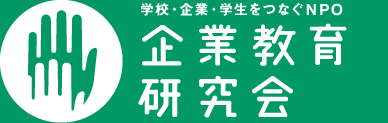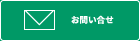2025年4月19日(土)に第168回「千葉授業づくり研究会」が開催されました。今回のテーマは、「就職やライフキャリアの最新事情から、キャリア教育のアップデートを考えよう!」です。
キャリア教育は学校教育の中でも実施されていますが、授業内容やフィードバックの方法などにお悩みの先生も多いのではないでしょうか。
本研究会では、株式会社マイナビの栗田卓也さんと今井普彦さんをお招きし、近年の就職活動の最新事情や、今後の社会で自立的にキャリアを構築するために必要な資質・能力、企業と連携した探究学習の例などをお話いただきました。かつての就職活動の常識とは異なる情報の連続に、驚きの感想を寄せる参加者の方もいらっしゃいました。
また、会の後半では、千葉授業づくり研究会定番のディスカッションを実施しました。実際にキャリア教育に関わる先生からのお悩みも寄せられ、実践的なテーマの議論となる場面もありました。
◆日本におけるキャリアの変遷および就職活動最新事情
はじめに、30年以上雇用や採用に関わる業務を担当し、マイナビ編集長として就職市場について調査・説明する立場も経験してきたという栗田さんより「日本におけるキャリアの変遷及び就職活動最新事情」の講演をしていただきました。
かつての日本では職業選択によって今後のキャリアが直線的に決まっていく傾向がありましたが、近年では多様な選択肢の中から自分に合うものを選べるように変化しています。テレワークや副業など、自由度の高い働き方が普及していることも背景にあるようです。
将来の選択肢の幅が増えるのは喜ばしいことではあるものの、これからの時代では1人1人がより主体的にキャリアと向き合う必要があります。
栗田さんには、近年の新卒就活や転職市場のトレンドをご紹介いただき、そのうえで、今後の社会でのキャリア構築に必要な資質・能力をお話いただきました。参加者からは、自分の就職活動と大きく違うことに驚く声も寄せられました。
ここからは講演の様子を抜粋しながらご紹介します。ライフキャリアやキャリア教育は、教育現場に関わる先生はもちろん、就職・転職活動中の方やわが子の就職活動が気になる保護者、進路に悩む学生など、幅広い方に関わるテーマです。ぜひ、最後まで読んでくださいね。
◆新卒就職市場の動向と学生の価値観

講演の前半では、新卒就職市場の動向と学生の価値観について栗田さんにお話しいただきました。
まず、2025年卒の採用充足率は70.0%で、約10年の調査では過去最低となっています。「人がほしいけれど、充分に確保できない」という状態のため、インターンシップや仕事体験、初任給引き上げを通じて、各企業が学生にアピールする動きが見られているそうです。
特に、大卒初任給は2020年卒の平均は226,000円でしたが、2023年卒では237,300円と1万円以上も増加しており、ここ20年では見られなかった動きだそうです。加えて、これから26年卒の初任給の引き上げを予定する企業は54.1%で、半数を超えています。これは25年卒の場合と比べると6.9ptも増加しています。
また、インターンシップや仕事体験の実施率も高くなっており、約5割の企業が実施しています。なかでも上場企業では7割が実施しているそうです。学生のインターンシップ・仕事体験の参加率も85.3%、平均参加者数5.2社と高く、過去最高水準の数値です。特に、最近では長期プログラムや実務体験ができるプログラムの参加率が増えており、ゆるやかに段階を経ながら自分のキャリアを考えるきっかけともなります。
また、インターンシップや仕事体験自体も年々参加者が増え、これらの活動を経て就職活動をする学生も多いです。さらに、インターンシップをきっかけに内定を得る動きもみられています。
一方、学生が企業をじっくり選べる環境であるものの、2020年卒からは企業選択のポイントがやりたいことから安定に逆転し、安定している会社を選ぶ割合の方が多くなっています。この背景には、老後の貯蓄や景気悪化、年金制度への不安などがあります。
そのため、就職後に副業や投資といった別の収入源を得ることを検討している学生も多いようです。また、副業ができると、就職先の企業以外でも別のキャリアを築くことができるメリットもあるとお話いただきました。
◆転職市場と企業選択軸

次に、転職市場と企業選択軸についてお話いただきました。新卒の就職活動では「安定」が重視されますが、転職者の場合は「給与」や「勤務地」などの働く条件を重視する傾向にあることが特徴です。
現在、転職者は331万人で再び上昇しており、就職氷河期に及ばないもののこの10年で2番目の数字となっています。
新卒については、景気がいい時も悪い時も一般的に「3年3割」というような一定数の転職があるそうです。とはいえ、最近では転職しやすい環境になりつつあるため、ネガティブではなくポジティブな理由による転職の増加も感じられます。また、転職市場の全体的な変化については、20代の転職率は上げ止まっていますが、40代以上は微増傾向とのことです。
さらに、転職を考える理由には「給与」「仕事内容」「人間関係」「将来性」が上位になるとお話いただきました。転職先の決定理由には、「給与」以外に「勤務地」「休日休暇」「福利厚生」が上位になります。転職者の場合は新卒とは異なり実際に働いた経験がある層なので、企業に求める条件がより具体的です。
また、企業が中途採用の選考で重視するポイントは、経験よりも気質的特性の方がやや高いともお話いただきました。スペシャリストやリーダーシップが求められないわけではありませんが、一般的には主体性や傾聴力、発信力、問題解決力などが重視される傾向にあります。しかし、得意・不得意は人によって異なるものなので、学校での実践などで自身の特性を理解できるきっかけを与えられると、自分の特性を生かす方法という視点で進路を考えることができるのではないか、ともお話いただきました。
◆今後求められる能力とインターンシップ


次に、今後必要となる能力やインターンシップの現状をご紹介いただきました。
企業の採用活動では「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」の3つの能力から成る「社会人基礎力」が意識されることが多いそうです。特に、その中でも「前に踏み出す力」に含まれる「主体性」や「実行力」の要素を重視する傾向があります。しかし、業界や職種によって求められる能力は異なるので、自分の気質に合う職業を探すのがよいのではないかとも補足がありました。
続いて、インターンシップの研究について解説いただきました。インターンシップは自己探索や環境探索を伴う「キャリア形成活動」として捉えられます。
共同研究による学生にとってのインターンシップの効果として5つ抽出されたのですが、特に、自分のやりたいことやキャリアプラン、目標が明確になる「キャリアの焦点化」と、社会の多様な選択肢や、業界・企業の理解など学生の視野を広げる「キャリアの展望化」の面で影響があったようです。
また、インターンシップを企業が実施する場合には、学生がインターンシップの「事前事後学習」がセットになっていることと「社会人基礎力」を通じた経験ができるプログラムであると、インターンシップの満足感や志望度、インターンシップを経た教育効果が向上する傾向があります。学生が事前にプログラムの内容を理解した上で活動に参加するため、就業体験で学生自身が学んでいることやこれから学ぶ必要があることを理解しやすくなるのです。
さらに、参加者の学生の成長を学生本人に伝えられる機会やメンターの存在も重要です。学生自身がインターンシップでの成長や自分の理解度を知るきっかけになり、これもインターンシップによる教育を高めるでしょう。
◆今後のキャリア形成で大切なこと

これらの最新事情を踏まえたうえで、最後に栗田さんより今後のキャリア形成で大切な点をまとめていただきました。
これまでは1つの職業選択で住む場所や家族の選択肢が絞られている傾向がありましたが、テレワークや副業が普及している現代では選択肢が豊富になっています。過剰な選択肢から自分の選択に意味づけをして、自分なりにキャリアをつむいでいくことが重要です。
加えて、「常に自分と対話しながら、自分の選んだキャリアを考え選び続けることが大切」ともお話いただきました。
これからのキャリア教育では、キャリア形成の方法が昔とは大きく変容していることを把握した上で、多様な選択肢の中から子どもたち自身が自主的にキャリアを考えるための働きかけが重要となるのですね。特にこれからのキャリア教育に関わる先生方にとっては、大切な視点ではないでしょうか。
◆企業と連携した探究学習の紹介
続いて、探究学習や高校生向けの事業に携わった今井さんより「企業と連携した探究学習について」のテーマで講演いただきました。
「探究学習」とは、「学習者が問いに答える学習を通して、知的創造を行う学習方法」を指します。探究学習では、自ら問いを立てて解決するための、「課題の設定」→「情報の収集」→「整理・分析」→「まとめ・表現」のプロセスが重要です。探究学習では課題解決型の授業が行われることが多いように感じるともお話いただきました。
また、今井さんは、高等学校の先生より探究学習の指導において次の3点についてよく相談を受けたそうです。
①生徒が問いを立てられない(学習の1歩目)
②学習成果やプロセスに対して、フィードバックや評価がうまくできない
③探究学習等の指導の経験差が出やすい
これらを踏まえて、マイナビでは企業の立場で、探究学習をサポートする取り組みを実施しています。今回は、具体的な事例を3つご紹介いただきました。
マイナビキャリア甲子園
まず、マイナビでは、高校生のビジネスアイデアコンテストである「マイナビキャリア甲子園」を実施しています。
本コンテストは、協賛企業が出題したテーマの課題を解決していくビジネスコンテストです。いくつかある協賛企業が出題したテーマに対して、高校生のチームが好きな企業テーマにエントリーします。その後、書類審査やプレゼン発表を経て企業代表チームを目指し、最終的には企業代表チームが集まり決勝戦が行われるというもの。
探究学習では、学習のはじめに生徒自身が問いを立てるのが難しいのが課題です。「マイナビキャリア甲子園」の場合は課題解決型のコンテストであるため、問いを立てるのが難しい学生でも取り組みやすい魅力があります。
高校生の探究学習教材「Locus」
次に、高校生の探究学習教材「Locus」を紹介いただきました。本教材は、高校の3年間の学びに合わせた探究教材となっており、下記のように段階的に学習を深めることができます。
「自己分析」→「地域を知る」→「業界を知る」→「企業を知る」→「学問を知る」→「自己実現へ」
Locusでは身近な地域の課題に向き合うことを契機として、企業や学問の関心へつなげていきます。
また、探究学習プログラムの中では、業界探究教材の「業界探究の1PPO!」という教材が使用されます。本教材は、「流通・物流編」や「半導体編」、「自動車編」など様々な業界をテーマに幅広い仕事を紹介する教材で、高校生の職業に対する視野を広げる狙いがあるそうです。
高校生ではなかなか仕事内容や業界のイメージがわきにくい仕事も取り上げられているので、高校生のキャリア選びの幅を広げるのに役立ちます。
探究添削サービス、小論文(地域型)添削サービス
最後に、添削サービスについて紹介いただきました。生徒が入力・記入した内容に対して専任スタッフからフィードバックをもらうことができるサービスです。
このサービスは、探究学習における「フィードバックの難しさ」という課題を解決するために開発されました。
また、前述した「マイナビキャリア甲子園」のようなビジネスコンテストの多くは、勝ち進んだチームの生徒しか審査員からの評価やフィードバックを受けられず、落選者は学習を振り返るためのヒントや機会が得られないという課題がありました。
そのほかにも、地域をテーマに発表や成果報告を行う探究学習の場合では、地域の人には喜んでもらえるものの、教育としてのフィードバックが少なくなってしまう課題もあるそうです。
こうした背景から、探究学習の過程や成果について専任スタッフによる添削を受けられるこのサービスは、多くの生徒が学校の先生や地域の人以外からの客観的な評価を受ける貴重な機会となります。
◆ディスカッション


研究会の後半は、千葉授業づくりでは定番のディスカッションの時間です。オンライン上で質問ができるサービス「Slido」を用いて、参加者と登壇者で議論を行います。今回は、実際にキャリア教育に携わる先生からの質問や悩みも寄せられました。
ここからは、ディスカッションの内容を一部抜粋要約してご紹介します(敬称略)。
Q.中学生の職場体験についてはどう考えていますか?受け入れ先となる企業によって温度差が大きいように感じられます。また、体験して終わりになってしまうこともあると思います。
(今井)企業の受け入れ状況については差があるのは事実です。また、参加する学生によっては学びの差が出てしまう実態もありますね。特に、中学生くらいまでの子どもだとなぜその会社に行くのかという動機づくりが難しいことがあるので、事前事後学習でどのような学習効果を得られるかを考えるのが大切です。
たとえば、中学生に新聞記者になって取材をしてもらうような授業はいかがでしょうか。中学生自身のキャリアで興味を持つことが難しくても、職場体験に行く動機づくりができると考えています。
(参加者)中学校でリクルートのタウンワークのようなものを作る授業実践の経験があります。企業の方や社長に中学生が名刺を渡して取材のアポ取りをし、働く内容や働きがいをタウンワークの求人一覧のような形式で地域に届ける授業内容でした。単に職場体験をするよりも、中学生なりに課題を見つけて考えることができていたように感じます。
Q.高校教員です。勤務校ではキャリア教育をほぼ実施できていないです。3年間でどの程度時間を取るとよいでしょうか?
(今井)Locusを使った学習の場合、事前学習して企業を訪問しアウトプットする流れで行われることが多いですね。年間12〜15コマくらいで実施されるケースが一般的です。丁寧に授業を行えば、さらにコマ数が増えていくことも考えられます。
(こちらの質問をきっかけに、動機づけについても話が膨らみました)
また、高校生へのキャリア教育の動機付けが難しい問題だと考えています。高校生にとっても、将来が大事だとかいうのは分かるけど、受験もあると考えているでしょう。生徒がやる気になるようにどう落とし込むか工夫をすることが大切で、例えば、国語の授業の小論文と関連させて探究学習を行うと「キャリア教育が入試でも使えるかもしれない」と興味関心を持たせられるんじゃないかな、と考えます。
(栗田)興味関心をちょっとでも持たせることがまずは一番と感じます。それを意識すれば授業プログラムの作り方や時間配分は大きく変わってくるのではないでしょうか。
例えば、韓流にしか興味がないような生徒に、BtoBの素材会社が面白いと伝えてもなかなか困難だと思います。それよりも、例えば、その関連のCM会社を紹介するなど、生徒が展望化できるよう、視野を広げられるよう支援し、選択肢と結び付けて理解してもらうようなことが大切だと感じます。
Q.最近は将来の不安から成長意欲がある学生が多いという話がありましたが、一方ではワークライフバランスを大事にしていて副業やテレワークができる会社が人気なイメージもあります。どのように学生の実態をとらえていけばよいか知りたいです。
(栗田)たしかに、仕事と私生活のバランスを大切にする傾向があります。現在の若い方は、男性でも育休取得が当たり前の世代です。
そのため、夫婦共働き前提でどちらかが休んだ時にも生計を立てられるように、結果としてワークライフバランスや自己成長の機会を求める方が増えていると思います。
以上で、第168回千葉授業づくり研究会のレポートのご報告とします。ご講演いただきました栗田さんと今井さん、そして参加者のみなさま、誠にありがとうございました。
千葉授業づくり研究会の参加方法
千葉授業づくり研究会にはどなたでも参加できます。
興味がある方は、こちらの開催情報をチェックしてくださいね!Zoomを用いたオンライン配信による参加もできるので、遠方の方も大歓迎です。
【記事担当:千鳥あゆむ】