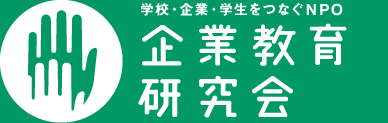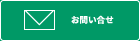2024年11月16日(土)に開催された、第166回「千葉授業づくり研究会」。今回のテーマは、近年注目のメタバースとも関連する「学校教育におけるVRの活用を考える」です。VRを用いてインターネット上の仮想空間に入ると、その場にいるかのような没入感を感じることができます。今では、学校教育の場でもメタバースやVRの活用が検討されています。
今回は、Meta日本法人Facebook Japanの栗原さあやさんにメタバースのビジョンやVRの教育活用などをお話いただきました。さらに、VRヘッドセットである「Meta Quest」の体験会や横浜市立東高等学校の黒木京子副校長による実践のご紹介も行われました。
この記事では、研究会の様子をレポートしていきます。VRやメタバース、最新技術を用いた教育に関心のある方は、ぜひチェックしてくださいね。
◆栗原さあやさん講演「学校教育におけるVRの活用を考える」

今回の千葉授業づくり研究会は、「学校教育におけるVRの活用を考える」がテーマ。
Meta日本法人Facebook Japanの栗原さあやさんにMetaの考えるメタバースのビジョンやVRの教育活用などをお話いただきました。さらに、横浜市立東高等学校の黒木京子先生にはメタバースモデル校での実践の様子や課題もご紹介いただきました。
ここからは、研究会の様子を抜粋しながらまとめていきます。
◆メタバースのビジョン

Metaは「人と人の“つながり”の未来とそれを可能にするテクノロジーの構築」をミッションとしています。同社のFacebookやInstagramなどの提供サービスには人々のつながりを大切にしたものが多く、今では全世界で32.9億人ものユーザーに利用されています。
「メタバース」は、SNSやコミュニティなどソーシャルテクノロジーの次なる進化の形を指します。Metaとしては、メタバースを「人と人をつなぐソーシャルテクノロジーの次なる進化」だととらえており、物理的な世界ではできないことを可能にして大切な人とより深くつながる、相互接続されたデジタル空間だと考えているそうです。
メタバース空間であれば、離れた場所にいる人たちでも相互にコミュニティに参加できます。加えて、没入感のある体験や相互運用性もメタバースの特徴です。
数年前だとテキストや画像が中心だったデジタルコンテンツの共有も、今では動画の割合が高くなっているようです。そして、今後は、VRやARのような没入感のあるコンテンツの共有が増えることをビジョンとして考えているともお話いただきました。
そして、Metaではメタバースの実現をテクノロジーやツールの強化でサポートしているそうです。たとえば、VRヘッドセット「Meta Quest」シリーズやソーシャルVRプラットフォームである「Meta Horizon Worlds」の開発もMetaが担っています。
◆VRの教育利用・活用事例

栗原さんにはVRの教育利用や活用事例もご紹介いただきました。Metaでは、新しいテクノロジーを教員の代替手段とするのではなく、教員が得意な「教える」方法を技術でサポートすることを目指しています。技術には正解の使い方があるわけではないので、先生たちや開発者などで一緒に考えていくのが理想的です。
また、メタバースの没入型の体験は、動物の解剖実験のシミュレーションにVRを使うなどの「コスト削減」や登校が難しくても遠くから授業に参加できる「アクセシビリティの向上」、さまざまな学習者が同じ土俵で学べる「公平性の向上」などの利点をもたらします。
このようなメタバース空間を利用することで、より多くの人たちの学習へのアクセス向上が期待できます。また、VRの没入感で集中しやすくなる例や語学学習でデスクトップよりもVRのほうが高い定着率であった事例など、VRによる教育的なメリットも紹介されました。
さらに、栗原さんには、実際の教育現場でのVR活用の例として、角川ドワンゴ学園でのVRを使った教科学習や部活動の様子をご紹介いただきました。Metaと同校の連携のもと、XRクリエイター育成の取り組みの一環として、「メタバース学園ドラマ制作プロジェクト」というプロジェクトも実施されたそうです。
加えて、横浜市消防局での活用事例もお話いただきました。近年では、知識や経験を積んだベテランの消防隊員が減り、経験の浅い若年層の隊員が増えているそうです。若年層が経験を積むためには訓練が必要ですが、火災件数自体が減る中、火を使った訓練はCO2を排出するため頻繁に実施できません。このようなときにVRを使えば、火を使わずに現場に近いシチュエーションで若年層が経験を積むことができます。
◆黒木京子先生による取り組み紹介
「未来の学びに挑戦 メタバースモデル校の取り組み」

横浜市立東高等学校 副校長の黒木京子先生にも勤務校での実践をお話いただきました。
横浜市立東高等学校では、メタバースモデル校として実際の教育現場でのVR活用を試行錯誤しています。今年8月にVR授業用の部屋の改装を終え、9月以降にはPTAや他校の校長先生、一部の生徒にヘッドセットをつけてVRの体験会を実施したそうです。
また、横浜市では「グローバルモデル校」という国際的な人材を育てるためのプロジェクトも実施されており、横浜市立東高等学校では国際交流の中でメタバースを活用する準備を進めている段階です。ですが、その準備を進めつつも、国際交流の用途に限らず、通常の授業や学校生活などでもVRを活用しています。
講演のなかでは、社会科の授業で「囚人のジレンマ」を行った際にVRでアバターを用いるとアナログの時と比べてゲームの結果に性差がなくなった事例や、家庭科の授業で消費者庁のVR動画を臨場感たっぷりに視聴した様子をご紹介いただきました。
実際に教育現場でVRを使用することで、子どもたちは大人よりもVRへの慣れが早かったそうです。Meta Questの使い方を教員から軽くレクチャーされた高校生が、2時間後の中学生見学会では中学生に教えてしまうほどの対応力だとか。
とはいえ、閲覧コンテンツの把握方法やネット環境・ヘッドセットの管理、教員研修、機器の準備、VR酔いなどの課題もあります。
ヘッドセットとコントローラーの管理の面では、複数台数のMeta Questヘッドセットとコントローラーが混在しないように、機器に番号が書かれたテープを貼ってアナログで管理しているという話や、授業にMeta Questを導入する際に、初回は子どもたちが大盛り上がりで体験に時間がかかるため、授業の進行を試行錯誤しながら実践を進めているとのお話もありました。
今後、実際にヘッドセット等を授業で取り入れる際、事前に把握しておくとよいヒントをたくさんお話しいただきました。
◆Meta Questを使ってVR体験会!離れた部屋からハイタッチ

研究会の中では、「Meta Quest」を用いて「Meta Horizon Workrooms」というバーチャル会議室アプリの体験会も行われました。「Meta Horizon Workrooms」はバーチャル空間の中で会議やおしゃべりができるアプリです。体験会では「Meta Quest」を初めて体験する参加者が多く、大盛り上がりの時間となりました。
体験会の参加者は3つの教室に分かれて各部屋の「Meta Quest」ヘッドセットを装着します。同じバーチャル空間に別の部屋から集合し、各々のアバターとのハイタッチやおしゃべりを楽しみました。参加者からは「それぞれのアバターのいる場所から声が聞こえるので、その場で話しているかのような臨場感がある!」との感動の声も。

また、体験会では会場のWi-Fiが不安定で接続に時間がかかる場面もありました。実際に教育現場に導入する場合には、機材の導入に加えて必要台数が問題なくネット接続できる環境整備も重要となりそうですね。黒木先生によると、横浜市の勤務校でも接続環境が万全とは言い切れない場面もあるようです。
◆VRを使ったアイデアが飛び交うディスカッション

研究会の後半では、千葉授業づくり研究会では定番のディスカッションを実施しました。オンライン上で質問ができるサービス「Slido」を使用して、参加者と登壇者で議論を行います。今回は、学校でのVR活用についてのアイデアも多く、活発な議論が行われる時間となりました。
ここからは、ディスカッションの様子を一部抜粋要約してご紹介します(敬称略)。

Q.VRを学校と家庭で繋いで使う場合、児童生徒の各家庭にヘッドセットなどの機器が貸与されるのですか?
(黒木)メタバースの空間に入るだけであれば、ヘッドセットがなくてもパソコンやスマホから入室し、チャットなどを楽しめるアプリもあります。
Q.VRを使えば子どもたちが保健室などで悩みを相談しやすくなりますか? 実際に養護教諭として勤務をしていると、悩みを相談するために保健室に来ることができずに不登校になってしまう子を見ます。
(栗原)学校とは別ですが、精神科医の方がアバターを使って相談を受けている事例があります。相談者が自宅からアバターの姿で話すことができるという面で、相談のハードルが下がる部分もあると考えます。
(黒木)ちょうど勤務校の養護教諭からもそのようなリクエストが来ていました。子どもたちの中には悩みがあっても「保健室に行く様子をほかの人に見られたくない」と感じる子もいるので、VRでの相談室があるとよさそうですね。
VRを活用した教育利用や活用事例の豊富な説明やモデル校の取り組みのご紹介、「Meta Quest」の体験会などを経て、議題や提案が次々と出てくるディスカッションとなりました。
黒木先生からは、横浜市立東高等学校で検討したことのある案として「音楽の授業で、オーケストラの楽団に入り込んだように感じられる空間で楽器を演奏できないか」「物理の授業で、光の速さをどのくらいの速さなのかを体感できる」「化学の授業で、危険な薬品を使う実験をVRで体験する」などのアイデアもご紹介いただきました。
最後に、ディスカッションで出てきたアイデアの一例をご紹介します。ぜひ、参考にしてくださいね。
・数学で立体物をバーチャル空間でつくる
・建物の高さをバーチャル空間で測定できるようにする
・心理的に厳しい動物の解剖などをVRで行う
・職業体験や修学旅行をVRで行い、体験の格差を補う
・アバターを使った自己表現や面接練習
・物理の光の速さの授業で、VRを使って月と地球でテニスをして光の速さを体感できる教材
・VRを使ってエンジンや細胞の中などに入ってみる教材 など
結びになりますが、ご講演いただきました栗原さん、黒木先生、参加者のみなさま、誠にありがとうございました。
【記事担当:千鳥あゆむ】