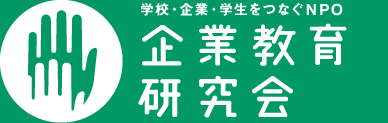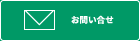10月19日(土)に開催された、第165回「千葉授業づくり研究会」。
今回のテーマは、「授業づくりにおける表現と差別・ステレオタイプを考える ~想像と創造のサイクルの中でジェンダーや人種をどう考えるか~」です。
昨今、テレビや映画、漫画からポスターまであらゆるコンテンツにおいて、その表現が人種やジェンダー、セクシュアリティの観点から差別的であると批判の対象になることがあります。これは教材や掲示物など、実は日常的に教育コンテンツを制作している教育現場にも起き得ることで、自分が意図せず差別的な表現をしていることがあるかもしれません。多様な子どもたちが存在する教育現場で、私たちはこれらにどのように向き合っていけばよいのでしょうか。
それらの課題を考えるため、今回の研究会では、ハリウッド映画における多様性やフェミニズムなどを中心に研究される東京大学大学院博士課程の山本恭輔さんをお招きしました。
まずは山本さんより、エンターテイメント産業におけるコンテンツ制作という視点を中心に、ジェンダーや人種の多様性と差別についての基礎的な内容から、最近の多様性やフェミニズムに関する世界動向まで幅広くお話しいただきました。そして後半、教育コンテンツ制作という視点でそれらの知見をどう活かしていくのか、参加者全員で議論しました。
タイトルにある『想像と創造のサイクルの中でジェンダーや人種をどう考えるか』とはどういう意味なのでしょうか。
本blog記事では、山本さんの講演とその後のディスカッションの中から、教育に関わる方々にお届けしたい内容を抜粋し、ボリューム多めですが、レポート風に紹介することにしました。広く深い知見を要するこの難しい課題に対し、この記事が教育現場の方々の一参考になれば幸いです。
◆山本恭輔さんについて
東京大学大学院博士課程で「メディア表象」を研究される傍ら、立教池袋高等学校でも社会学の教員として男子校の高校生に多様性について教えている山本恭輔さん。
実は山本さんは、企業教育研究会(ACE)に深いかかわりのある方で、山本さんとACEの出会いは12年前まで遡ります。当時中学生且つデジタルネイティブ世代であった山本さんに、ACEで開催したメディアリテラシー研究会の講師をお願いしたことも。その後もずっと活動に関わって下さり、現在は、ACEが関わるドラマ教材制作等にて配慮事項について監修や、ACEの理事もしていただいています。
-1024x693.jpg)
◆創造のCG画像を、なぜ世界中の人が特定の都市「東京」と想像できるのか
~私たちの認識の特徴と、偏見・差別との関係性について~
まず山本さんは、CGアニメーション映画で使用された東京、ロンドン等がイメージされるCG画像を示し、なぜこれらを特定の都市だと感じるのでしょうかと問いかけました。なぜ、CGで作られた画像を、私たちは例えば東京だと認識するのでしょうか。実際に行ったことが無くても、万人に東京という同じものを想起させるということは、どういうことなのか。
私たちは、何かを表現して伝える時、複雑なすべてをそのまま伝えることはできないため、意識的(半意識的)に大量の情報の中からどんな要素を抽出するか選択をしています。また逆に、私たちは何かを見た時、複雑なすべてをそのまま知覚することはできないため、「想像」し認識を「創造」しています。
このように、あるものを、別のなにか(記号)に置き換えて表現することを「表象(ひょうしょう)・representation」と言います。
例えば、東京タワーや富士山、ネオン街といった記号が東京らしさを特徴づけるものとして使われ、その表象が流通することで、人々の想像力の中で「東京」というイメージが広く共有されていきます。すると、逆にその記号がある表象に対し、人々は東京を想起するようになります。
ハリウッド映画などで東京を描く際には、この現象を利用しているということになります。もちろん東京以外のあらゆるものを描く際にも同様なことが起きています。
ではなぜ、このような記号で特定のものごとを表象できるのでしょうか、そしてなぜ、我々はそれを認識することができるのでしょうか。
われわれの認知機能は、知覚する人や物を、一定の特徴に基づいて「カテゴリー」に分類します。
そして、特定のカテゴリーが共通して持っていると信じられている特徴のことをステレオタイプと言い、そのステレオタイプを用いて他者を判断するステレオタイプ化は、人間の認知機能の節約として無意識で行ってしまいます。
つまり、例えば東京タワーはカテゴリーとしては「都市東京」を特徴づける記号であり、CG画像に東京タワーを描くことで他者に東京と判断させることができます(ステレオタイプ化)。
ステレオタイプ自体はニュートラルなものですが、そこに否定的な感情や評価が結びつくと偏見となり、偏見が元になった否定的な判断が相手に対する言動や行動として現れると差別となります。
ステレオタイプによる判断が無意識に出てしまう以上、そのステレオタイプを偏見や差別へ繋げないためには、自分自身が他の人や物を、どのようなステレオタイプで眺めているかについて自覚的になることが必要です。
※ジェンダー・フェミニズム・セクシャリティ・人種に対する基礎的講義もありました。その内容についての参考資料はコチラ(配布資料より)。
◆想像と創造のサイクルの中でジェンダーや人種をどう考えるか
~私たちが意識すべきこと~
山本さんより、「自分自身が他の人や物を、どのようなステレオタイプで眺めているかについて自覚的になることが必要です。」との指摘がありました。それに対し私たちは、『いろいろな選択肢の中から個人で自由に選択しているように見えても、実は自分が見聞きしてきたものに影響を受けている。』ということを、今以上に意識する必要があります。
例えば、山本さんの紹介事例によると、フリー素材を提供するWebサイトいらすとやで「監督」を検索すると、女性に見える選択肢は監督官の1つしか出てきません。
このように画像検索した際、検索結果において性別により就いている職業に偏りがあったり、そもそも検索にヒットする頻度が低いとなればどのような印象を引き起こすでしょうか。これらが繰り返し使用されたり、また使用する選択肢のなかに用意されないことにより、人々はその選択肢がないことを当たり前に感じるようになってしまいます。
このように、制限された表象は、社会の特定のイメージを維持・再生産します。それが、想像と創造のサイクルです。
従って、制作者が意図するかに関わらず、それがどういう社会的意味合いを持つのか、どう解釈されるのか、その解釈によりどういう社会的認識に繋がっていくのか(他者をどのように判断することに繋がっていくのか)を意識し、ステレオタイプ化から偏見差別に繋げないことを意識的に行うことが大切です。
だからこそ、映画・テレビ・漫画などを「ただのフィクションだから」とは扱えません。
たかがイラストではないかとは言えないのです。
◆ハリウッド映画業界の動きと女性の描かれ方の変化
~最近の動向と、多様性に対する企業のスタンスについて~
山本さんより、映画『カーズ』3部作を事例に、2006年、2011年公開の2作目までは、ほとんどの女性は「男性との関係性」の中でのみ登場していたものの、2017年の3作目で新しく登場した女性は恋愛や結婚など男性との関係性が提示されず、必ずしも女性が異性愛的な関係における従属的な存在ではない、主体性持った存在として描かれるように変化したことが紹介されました。
また、ディズニー・プリンセスを事例に、かつて受動的で、男性の助けが必要な「白人」として描かれがちであったプリンセスが、現在は、活発で、必ずしも恋愛(結婚)せず、多様なバックグラウンドを持ったプリンセスとして描かれるようになっていることも紹介しました。
ただ、これらの多様化された描写は、企業にとっては、必ずしも社会的意義のみを目的としてはおらず、商業的な面でこれらに配慮していること自体が、ブランド化し利する面もあることにも触れました。また、時に利(売れるか売れないか)が優先され、例えば日本においては、未だに白人で女性性が強い旧来的なプリンセスを前面に押し出し商品展開をしており、そこに人種差別の意図があってもなくても、プリンセスにおける非白人の表象頻度が低くなることで、社会のイメージが旧来的なまま固定化されてしまっている現状についても触れました。
※表紙画像出典元:
Disney Princess The Essential Guide New Edition Victoria Saxon (著) DK Children
ディズニープリンセス パーフェクトガイドブック DK(編)増井彩乃(訳)Gakken
◆ディスカッションより
~教育コンテンツ制作を考える上で留意できること、すべきこと~
後半のディスカッションでは、前半の講演を踏まえ、教育現場で用いる教材・題材で留意すべきことや、それだけではなく学校生活での子どもたちへの影響など、幅広く意見交換する時間となりました。その内容について、いくつか紹介します。
◆参加者より◆
Q:学校において、生徒指導は男性教諭、教育相談は女性教諭、大きな行事は男性、そのサブは女性がやるものみたいなことを、子どもたちはこういうものだろうと感じながら日々成長しているかと思うと怖い気がしました。
(山本さん)目にするものが当たり前になってしまう面は否めないので、そうではないあり方もあることを、(生徒に)目にしてもらうだけでも違うと思います。また、そういうコンテンツを生徒に見せる際には、必ずしも共感を促すのではなく、こういう視点や声があることを意識して欲しいから見せるのだと、一定の客観性を担保して示すことは入りやすさもあり有効だと感じています。
Q:学校内でこれらのテーマを話し合える土壌を作るには?
(参加者の中には、学校でこのような話題を全く話したことが無い(話せる雰囲気ではない)という方もいれば、結構話題に上がるという方もいました。)
(山本さん)偏見や差別といった話題で会話するにあたり、個人の内面や思想の統制ではないという認識が必要だと思います。そういった認識をお互いにもった上で議論をしないと、「私は差別をしているつもりはない」、「思いやりが解決する」という方向になってしまいます。そうすると(日常生活における自分の言動について)「これは駄目なのか」的な話になりやすく、人によってはすごく統制されていると感じてしまう。
そうではなく、公共の場で差別を表出しないために最低限の線引きはこのぐらいになるということや、表現においてここは最低限守らないと、ということを議論する。その前提に立てるかが重要だと感じます。
Q:教材を作るにあたり、何に気をつければいいですか?
(山本さん)難しいですけれど、元も子もないことを言うと、何をやっても問題は起き得ます。問題が起きない選択はないです。その中で、どういう意義を持ってその選択をしたのか、その判断について説明可能かどうかということが大切なのではないかと考えます。
Q:意義をもって何かを選択するには、広く深い知見が必要かと思います。専門家ではない人が、留意できることはありますか。
(山本さん)専門家に頼ってくださいというのがまず一つですね。アクセス可能な専門家がいるかということはありますが、やはり、ACEや先生方といった授業をつくる方が、全てのことを100%把握できるわけではないので。だからこそ、専門家に頼るのが一番かと思います。
◆基礎的なことを学ぶに適した山本さんお薦めの書籍2点
・フェミニズム大図鑑 ハンナ・マッケン ほか (著) 三省堂
・クリティカル日本学 ガイタニディス・ヤニス (著, 編集) 明石書店
◆最後に山本さんより
結局、ディスカッションしていくしかないと思います。一方で、教材はどこかで折り合いをつけて完成させなければいけないので、実践一つ一つにどう折り合いをつけ、どう責任を持つのかは、すごく心が暗くなることもあります。
そこに関しては100%自信を持って何かを出すということは、正直できないということを受け入れる前提に立つしかないのかなと思います。
でも、例えば日本におけるディズニー・プリンセスの商品展開にあるように、どういうものが受け入れられると思うのかということに対して、やはり子どもたちに対して選択肢がある程度広がっていくことの大切さはあると考えています。


明るく活発な研究会となりましたが、今回のテーマは、とても根が深い問題を内包しており、例えばジェンダーという視点では、世間を賑わしたジェンダー・ギャップ指数や、女性管理職のクウォーター制などがあるように、これらは学校教育現場に限らず、日本社会が抱える課題でもあると思います。
私たちが日ごろ意識せず表現している様々なコンテンツが、これらの問題を固定化し、再生産している現状もきっとあるのだろうと感じますし、もし意識したとしても、自身の表現からその問題を完全に排除することも難しい。山本さんの話を聞き、大人である私たちが、既に子どもたちがニュートラルに捉えているものを、意識せず旧来的に選択肢を示してしまうこともあり得るという危険性も感じました。
そのような中で、これから社会に出ていく子どもたちに、どういう選択肢があり得ると示していくのか。子どもたちに日々接するACEとしても、葛藤を持ちながらも日々向き合っていきたいと思います。
と…、約20年前、新社会人1年目に感じたモヤモヤの解を求めて当時フェミニズム系の書籍を読み漁り、現在も一人の妻として親として模索を続ける本blog記事担当が感じたことを少しだけ吐露させていただき記事を結びたいと思います。
次々回、12月の千葉授業づくり研究会では、実際に葛藤を抱えながらも世に映像作品を発信し続けているスペシャルゲストをお招きし、さらにディスカッションをしていきます。