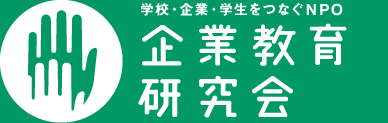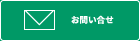2024年11月5日(火)、香取市立小見川東小学校4年生・6年生のみなさんへ、千葉県魅力ある建設事業推進協議会(CCIちば)とNPO法人企業教育研究会(ACE)の連携による出張授業 「千葉県の建設業の仕事」の「川とくらしを守る仕事」 を実施しました。
4年生の社会科、5年生の理科の学習に関連した、川の護岸工事の現場や災害復旧活動など建設業の仕事や役割を紹介する授業プログラム。
この記事では、当日の授業の様子を紹介します。
◆出張授業「千葉県の建設業の仕事」の授業プログラムとは
2013年度から、ACEはCCIちばの事業として千葉県内の小学校・中学校を対象に出張授業を実施しています。建設業は職場見学・職場体験が難しい業種の一つですが、街や暮らしの安全を守り、地域に根差した世の中に欠かせない仕事です。
出張授業では、ACEのスタッフが進行して、学校近隣の建設業の企業から参加するゲスト講師が解説をする形で授業を行っています。この日は、千葉県建設業協会・香取支部の企業のみなさまが、ゲスト講師として参加しました。
出張授業「千葉県の建設業の仕事」の詳細はコチラ
◆江戸時代から千葉県は建設業をやっていた先人がいた!
現在の千葉県は江戸時代から利根川・印旛沼の度重なる氾濫に悩まされてきた歴史がありました。かつて、治水でなんとかしようとした人物が、千葉県一部の4年生の教科書にも登場します。
その名は「染谷源右衛門」さん。染谷源右衛門さんは、利根川の水が氾濫したときに、東京湾に流れるように新川・花見川を掘り進めようと構想していました。江戸時代当時はうまくいかなかったこの工事が、昭和の時代に大和田排水機場として完成し、今は印旛沼の周辺も農地や住宅ができ、安心して人々が住めるようになったことを復習します。

◆現代でも川岸を守る工事をしている人がいる!
そして現在も、新川をはじめ様々な河川で川岸を守る工事が行われています。その様子を、現場の映像や写真を使って紹介していきます。
川岸を保護する工事に使われている「鋼矢板」を教室の中に持ってきて長さや重さを体感することで、川の水の力が大きいことを学びます。ゲスト講師から「作業は安全第一なので、作業する人の安全を守るために鋼矢板が使われている」ということに感心する子どもたち。


次に、この川岸では護岸にコンクリートや鉄ではなく、石と金属のカゴで保護する「かごマット」が使われている理由を考えます。そこには、ただ川岸を保護するだけではない、川とともに生きていく私たちの暮らしに関わる、子どもたちの想像を超える理由がありました。ゲスト講師が解説をすると、子どもたちだけでなく、先生方をはじめとする大人からも驚きの声が上がります。
◆ものづくりをしながら地域に貢献する「建設業」
最後に、護岸工事以外にも道路工事や上下水道工事などの現場があることや、働く人のやりがい、そして建設業は男性も女性も働きやすい仕事になってきていることを紹介する映像を視聴しました。
そして、ゲスト講師からも学校の近辺で行っている工事の様子や、災害時の復旧活動、普段仕事で使っている道具などを紹介してもらい、仕事のやりがいや魅力が語られます。
この授業を受けることで、工事現場を見かけたらどんなことをやっているか、関心をもってほしい。そして、将来の仕事の選択肢の一つにしてほしい。この出張授業は、そんな願いから、10年以上少しずつ内容を変えながら行われています。




【児童の感想より】
(アンケートより抜粋紹介・一部漢字に変換)
‣建設業は僕たちの毎日を支えてることが分かった。
‣建設業は僕たちのために住みやすい環境を作ってくれているんだなと思いました。将来この仕事をやりたいと思いました。
‣崩れいていなくても、いずれ崩れそうな川辺の補強工事をしていることが一番心に残りました。そしていろいろな意味があって川の補強工事の素材を選んでることもすごい、と思いました。
‣人の命や自然を守る大切な仕事が建設業なんだとわかりました。
【小見川東小学校 佐藤 ゆう子 先生より 】
4年生は、社会科香取市の地域につくした人々について学習しています。また、6年生は、キャリア教育で様々な職業について調べたり、体験したりして学習しています。
どちらの学年でもSDGsについて理科の学習で取り上げられており、たくさんの方の支えがあって今の暮らしが成り立っていることが体験を通して学ぶことができました。
児童の中には、建設業の仕事につきたいという女児がいます。身近な建設業の方に来校していただいたことや女性も働きやすい職場としても紹介していただいたので、自信をもって夢に向かって進めると思います。ありがとうございました。
授業の様子は、千葉テレビのニュースでも放映されました。ぜひご覧ください。
「千葉県の建設業の仕事」の出張授業プログラムでは、今回ご紹介した「「川とくらしを守る仕事」に加え、「建設現場で働く人たち」も展開しています。
【写真:松田康太郎】