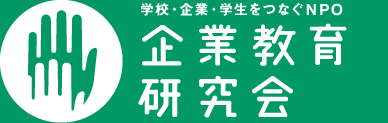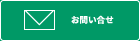NPO法人企業教育研究会(以下ACE)では、学校・学生(大学)・企業の三者が連携して誰もが教育に貢献する社会を目指し、所属する学生の研究支援も行っています。本ブログでは、ACEが支援を行った研究プロジェクト「生成AIリテラシーの育成を目的とした小学生向け授業プログラムの開発」の概要を、本研究を担当した弊会元学生スタッフ岡野がお届けします。
◆目次
1. 授業開発の背景 ―生成AIという「魔法」の登場―
2. 授業の内容 ―「魔法」の創り手へ―
2.1. 授業デザインについて
2.2. 2校での実践について
3. 成果 ―生成AIとの「ちょうどいい」 距離感を意識する―
4. 課題と今後の展望 ―今後の授業開発に向けて―
研究・執筆責任者:岡野健人https://kento-okano.studio.site/
千葉大学大学院教育学研究科修士課程修了・修士(教育学)。現代的教育課題について、実践的に研究している。生成AIの教育利用・エンターテインメントの教育援用・いじめ問題などのテーマに取り組む。元ACE学生スタッフ(2025年3月31日まで)。
協力校:四街道市立大日小学校、船橋市立金杉台小学校
協力企業:デル・テクノロジーズ株式会社
1. 授業開発の背景 ―生成AIという「魔法」の登場―
学術研究的な意義や背景については、論文等1で論じているため、ここではあえて異なる視点から、授業開発の背景について記したいと思います。
近年、生成AIが登場し、急速に発展しています。生成AIが自然な文章やイラストを生成し、流暢に話をする様は、まるで「魔法2」のようにも感じられます。この「魔法」の登場により、社会は大きく変化すると言われています。変化が及ぶ範囲は、日々活用するスマートフォンの機能から、知的生産の根本的なあり方に至るまで、様々です。
こうした情勢から、学校教育においても生成AIをどのように扱うべきかについて、盛んに議論されるようになりました。学会や実践報告会等の場で関連する実践が報告されており、生成AIへの注目度の高さがうかがえます。
他方で、報告される実践の多くが、私の目にはいささか「消費者」的にうつりました。生成AIを「ただ使うこと」を目的とした授業が多いように思えたのです。しかし、それでは生成AIという「魔法」の裏側をのぞいてみることはできません。もちろん、裏側をのぞかなくても、「魔法」を使うことはできます。むしろ、裏側を知らないからこそ生成AIがまるで「魔法」のように感じられる、とも考えられます3。
しかし、こと教育においては、「魔法」を「魔法」のまま扱えばよい、ということにはならないのではないでしょうか。裏側をのぞいてみて、仕組みを知ったり、「魔法」に頼り過ぎずに上手く活用する方法を考えたり、どうすれば「魔法」を使って社会を良くしていけるかを模索したりすることが重要となるはずです4。こうした学習を通して、「生成AIリテラシー」を身につけていくことが生成AI時代を生きていく子どもたちにとって必要となるのではないかと考え、今回の授業づくりをスタートさせました。
2. 授業の内容 ―「魔法」の創り手へ―
2.1. 授業デザインについて5
では、生成AIという「魔法」の裏側を授業で扱うには、どうすればよいのか。検討の末、今回の授業では、子どもたちが生成AIと「生産者」的に関わる機会を設けることにしました。具体的には、「学校で活用するための生成AIツール」を授業で開発するという文脈を提示し、子どもたちとともにツールの開発を行いました。こうした授業デザインを行ったのは、「生産者」の立場を体験することで、ブラックボックス化しがちな仕組みや開発・利用の際に大切な考え方を、ある種の「手触り感」とともに学ぶことができるのではと考えたからです。
とはいえ、当然ながら、子どもたちがすべての工程をこなすことは困難です。そこで、岡野・藤川(2023)が提案する教材を用いることにしました。この教材では、生成AIツールの開発プロセスの一部を、プログラミング等の専門的な知識がなくとも体験できる設計になっています。
また、こうした授業デザインのもとでは、児童は「生成AIツール開発者」という「専門家」の役割の一部を担うことになります。たとえ一部であっても、児童が「専門家」としての視点を持つことが求められるため、授業の中でその視点を適切に教示することが重要となります。
そこで、実際に生成AIや生成AIツールの開発を行っているデル・テクノロジーズ株式会社のAI SpecialistおよびCTO Ambassadorである増月孝信氏を講師として招き、一部の授業にご参加いただきました。
2.2. 2校での実践について
〇四街道市立大日小学校6
大日小学校では、全3時間の授業として実践を行いました。1時間目にはAIや生成AIについての基本的な知識を、デモンストレーション等を通して扱いました。2時間目には、1時間目の学習を活かしながら、生成AIツールに与えるデータの作成を行いました。3時間目では、増月氏の講演を通して、AIがもたらす社会・職業の変化や、AIの開発や利用には人間が重要な役割を果たすことについて学びました。2時間目までを通して、子ども達なりに考えを深めた後に専門家の話を聞くことで、より思考を深めるねらいがありました。
なお、大日小学校では、6年生最後の卒業制作という形で「図書室の本から1年生におすすめの本を教えてくれる」生成AIツールを開発しました。「お世話になった学校や1年生のため」という動機付けのもとで、一丸となって製作に取り組んでいました。


〇船橋市立金杉台小学校7
金杉台小学校では、全4時間の授業として実践を行いました。大日小学校での実践をもとに、ブラッシュアップした実践です。金杉台小学校では、異学年交流や読書指導を重点的に行っていたことから、大日小学校と同じく「図書室の本から1年生におすすめの本を教えてくれる」生成AIツール」を開発することになりました。1時間目は、変更なく授業を進めました。他方2時間目では、生成AIの仕組みについて詳しく扱うことにしました。また、生成AIツールが参照するデータにどのような内容を含めるのかについての話し合いを行った上でデータを作成する授業デザインにしました。3時間目では、生成AIや生成AIツールの使用を子どもたちが体験8し、課題解決を行う機会を設けました。4時間目には、増月氏からの講話やクイズに加え、未来にどんなAI技術が登場するかを想像し、それが社会にどんな影響を与えるか考える活動を行いました。
3. 成果 ―生成AIとの「ちょうどいい」距離感を意識する―
子どもたちが「生成AIリテラシー」を身につけるきっかけを提供できたことは、一つの成果です。これについては論文等9で論じていますので、ここでは別の観点からの考察を試論として記したいと思います。
それは、生成AIを「コンヴィヴィアリティ」のある道具として使いこなす視点を提供できたのではないかということです。「コンヴィヴィアリティ」とは、思想家Ivan Illich(1973)の提唱する概念です。緒方(2015)の解釈を踏まえつつ、概要を説明します。Illich(1973)は、あらゆる道具には「人間に力を与えてくれる第一の分水嶺」と、「人間から力を奪う第二の分水嶺」があるとしました。そして、第二の分水嶺を超えると、人間が道具を使っているようで「道具に使われる」ようになってしまうと言います。そうならないために、2つの分水嶺の間で「ちょうどいい」バランスを探ることが重要である、と言うのです。
生成AIが「ちょうどいい」道具なのかは、私にもわかりません。生成AIを使うと何も考えずとも宿題ができてしまうことを考えると、「第二の分水嶺」をはるかに超えた道具なのかもしれないとも思います(笑)。他方、道具が「ちょうどいい」かどうかを決めるのは、道具それ自体の特性だけでなく、「ちょうどいい」道具として使おうとする人間の意識も重要なのではないかと思うのです。
授業後アンケートでは、「AIは便利だけど頼りすぎないようにしたい」「人が中心であると忘れないことが重要」といった趣旨の記述が見られました。こうした記述は、児童が生成AIを「ちょうどいい」道具として使いこなそうとする態度の現れであると言えないでしょうか。
上記の考察はあくまで試論です。しかし、今後テクノロジーが発展していく社会において、「コンヴィヴィアリティ」という概念に示唆を得て実践を行うことは、ますます重要になってくると考えています。今後、こうしたことについてより考察を深め、研究を進めていきたいと思います。
4.課題と今後の展望 ―今後の授業開発に向けて―
今回の実践はACEの豊富なリソースや学校・企業様の多大な協力があったからこそ実現できたものです。今後は、いつどこの学校でも実践することができるようにパーケージ化していきたいです。また、小学校以外の他校種でも展開したいと考えています。こうしたことを踏まえて、授業をリデザインしていく所存です。
また、授業後の児童の感想の中に「AIに仕事を奪われる」ことに不安を覚えたという記述も散見されました。これからの社会を担う子どもたちが、未来に期待感をもつことができるような教育のありかたも非常に重要だと考えます。こうしたことを踏まえ、キャリア教育の文脈でAIをどのように扱うかについて模索していくつもりです。
◆参考文献
阿部学(2018)「「企業とつくる授業」の最前線―子どものハートに火をつける、「魔法」の授業をつくる!」, NPO法人企業教育研究会編『企業とつくる「魔法」の授業』, 教育同人社, 6-19.
Ivan Illich(1973) Tools for Conviviality, Marion Boyars.
緒方壽人(2021)『コンヴィヴィアル・テクノロジー ―人間とテクノロジーが共に生きる社会へ』, 株式会社ビー・エヌ・エヌ.
岡野健人・藤川大祐(2023)「独自データ活用型生成AIを利用した教育実践デザインの検討 ―生成リテラシーの涵養を目的として―」, 日本教育工学会研究報告集,JSET2023-2, 274-279.
岡野健人・藤川大祐(2024)「生成AIリテラシーの涵養を目的とした小学校向け授業プログラムの開発」, 日本教育工学会2024年秋季全国大会(第45回大会)講演論文集, 523-524.
岡野健人(2025a)「生成 AI リテラシーの育成を目的とした小学生向け授業プログラムの開発―オリジナル生成 AI ツールの開発を通して―」, 令和6年度千葉大学大学院教育学研究科修士学位論文.
岡野健人(2025b)「生成 AI について学ぶ小学生向け授業プログラムの開発 ―オリジナル生成 AI ツールの製作を通して―」, 授業実践開発研究, 18, 21-30.
落合陽一(2015)『魔法の世紀』, PLANETS.
1 岡野・藤川(2023)、岡野・藤川(2024)、岡野(2025a)、岡野(2025b)で論じている。
2 落合(2015)によれば、テクノロジーが発展することで、あたかも「魔法」のようなことを起こせるようになる。落合は、『2001年宇宙の旅』で知られるSF作家、アーサー・C・クラークの「十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない」という言葉を引用し、そのイメージを語っている。
3 落合(2015)曰く、「魔法」が「魔法」であるために重要なのは「無意識性」である。原理や動作機序を意識しないからこそ、「魔法」は「魔法」たりえる。
4 阿部(2018)による検討を踏まえた記述である。
5 本節でも、あえて研究とは異なる視座から論じることを試みた。
6 実践の詳細については、岡野・藤川(2024)を参照のこと。
7 実践の詳細については、岡野(2025a)・岡野(2025b)を参照のこと。
8 ChatGPTの利用規約を踏まえ、あくまで疑似的な利用体験にとどめた。詳しくは、岡野(2025a)、岡野(2025b)を参照のこと。
9 岡野・藤川(2024)、岡野(2025a)、岡野(2025b)で論じている。